
今回は『声が出る仕組み』と「声の4要素」についての内容です。
「声の4要素」をしっかりと理解しておくことで、歌のトレーニングに活かされるでしょう。
声が出る仕組み
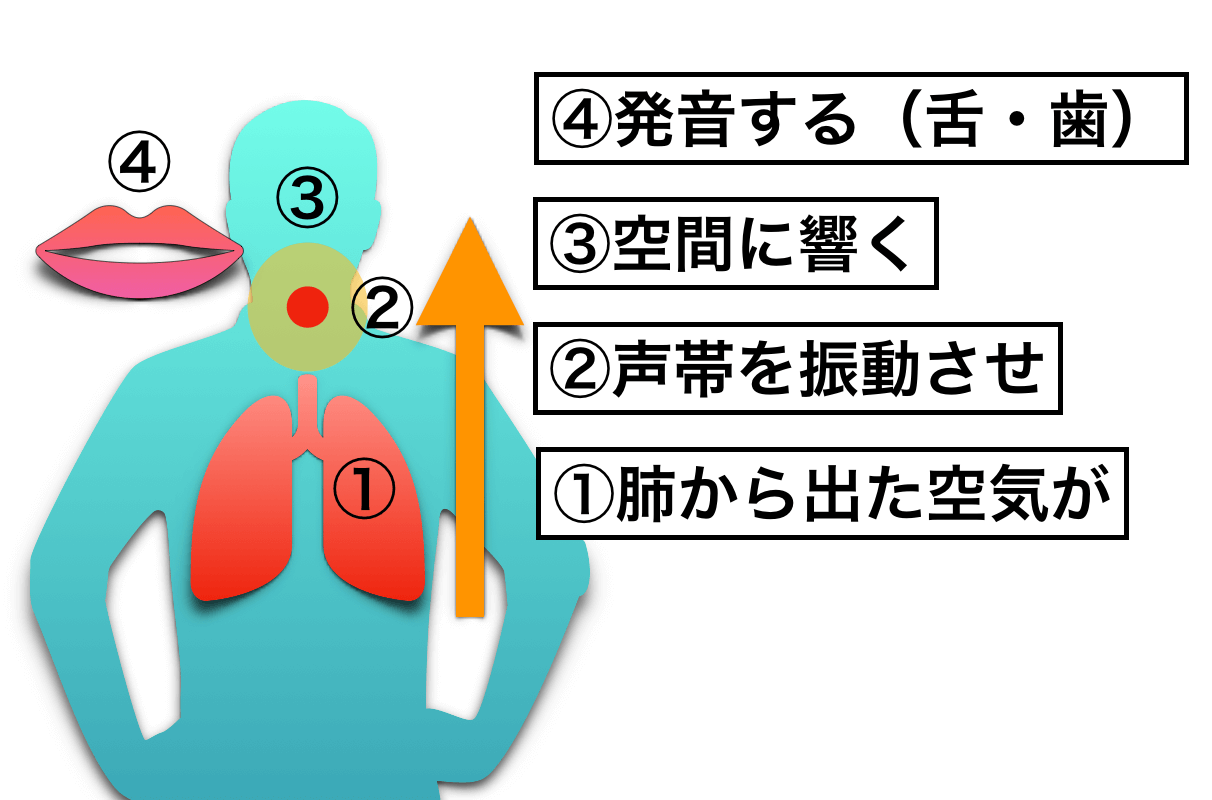
声は、
- 肺が空気(息)を送り出す
- その空気によって声帯が振して音が生まれる
- 生まれた音が空間(咽頭腔・鼻腔・口腔)に響く
- 発音によって音の種類が決まる
という順番で生まれます。
こちらの動画がイメージしやすいです↓
①肺から空気(息)が出る
人間は肺が膨らんだり萎んだりして息を出しているというのは、多くの人が理解していることでしょう。
肺を動かしているのは「横隔膜」や「胸郭」です。
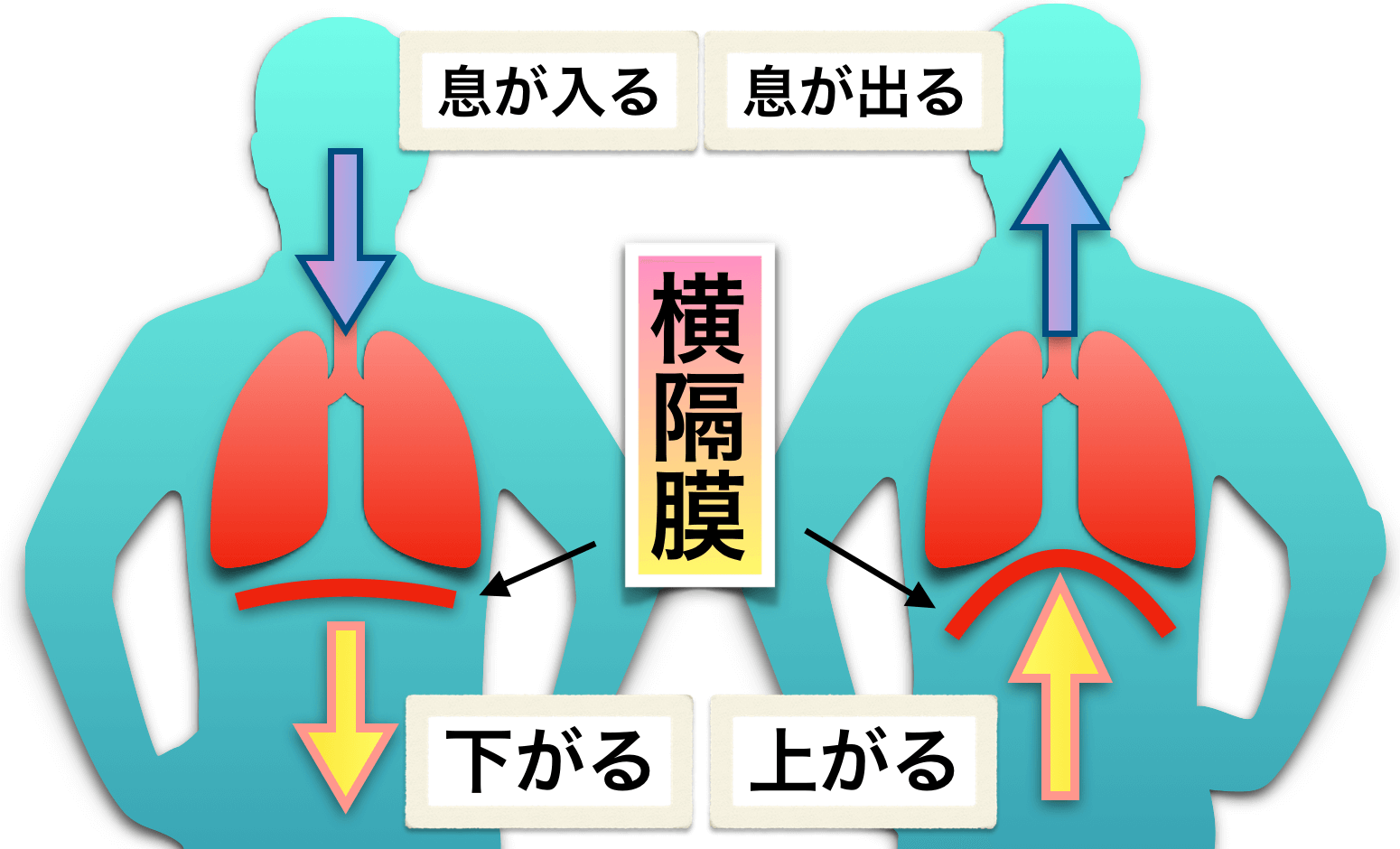
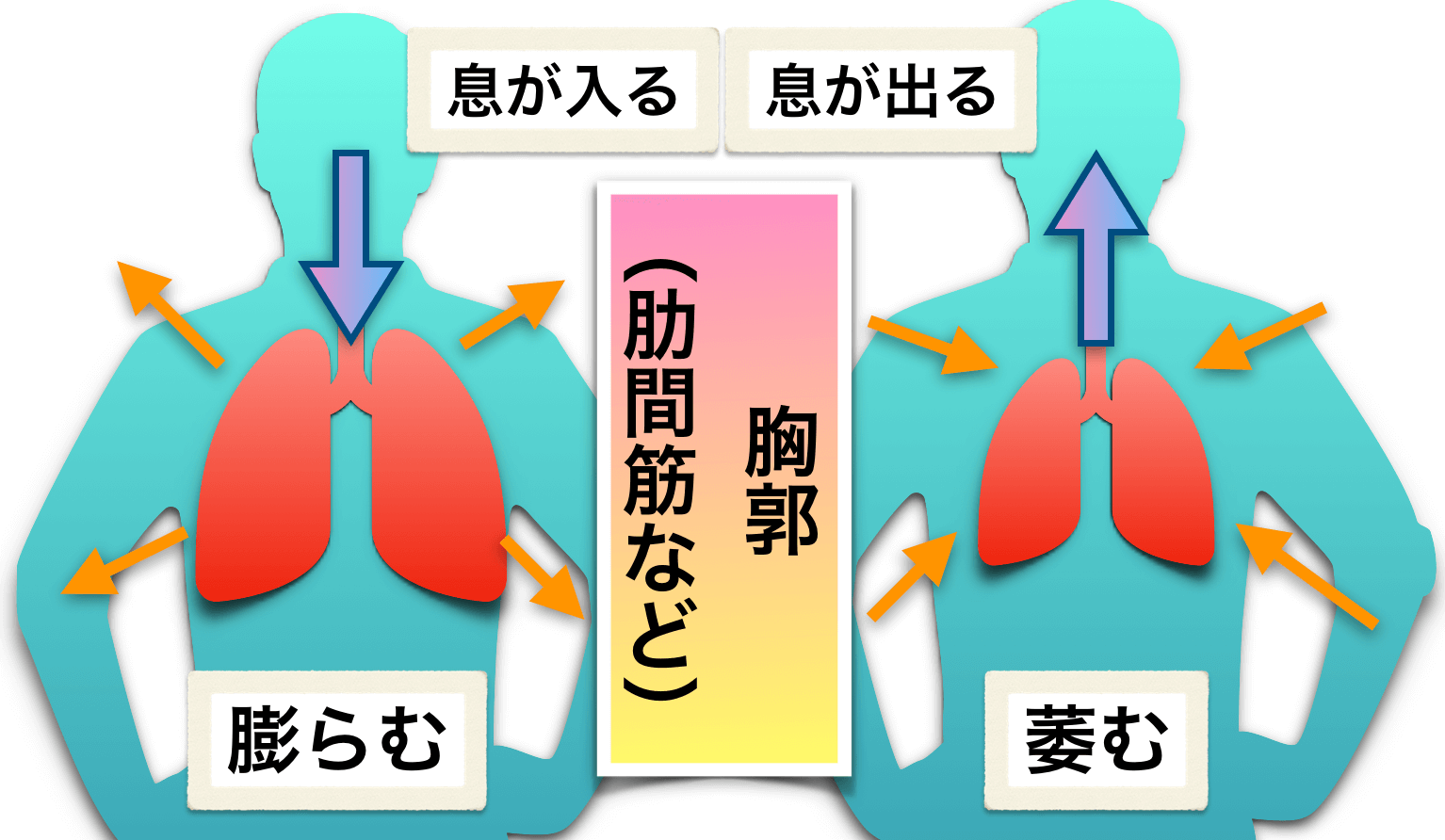
これらの動きによって、息を吸ったり吐いたりしているのですね。
-

-
肺活量と発声の関係性について【肺活量は歌に必要なのか】
続きを見る
②空気(息)によって声帯が振動する
声帯は、左右のヒダが開いたり閉じたりするような仕組みになっています。
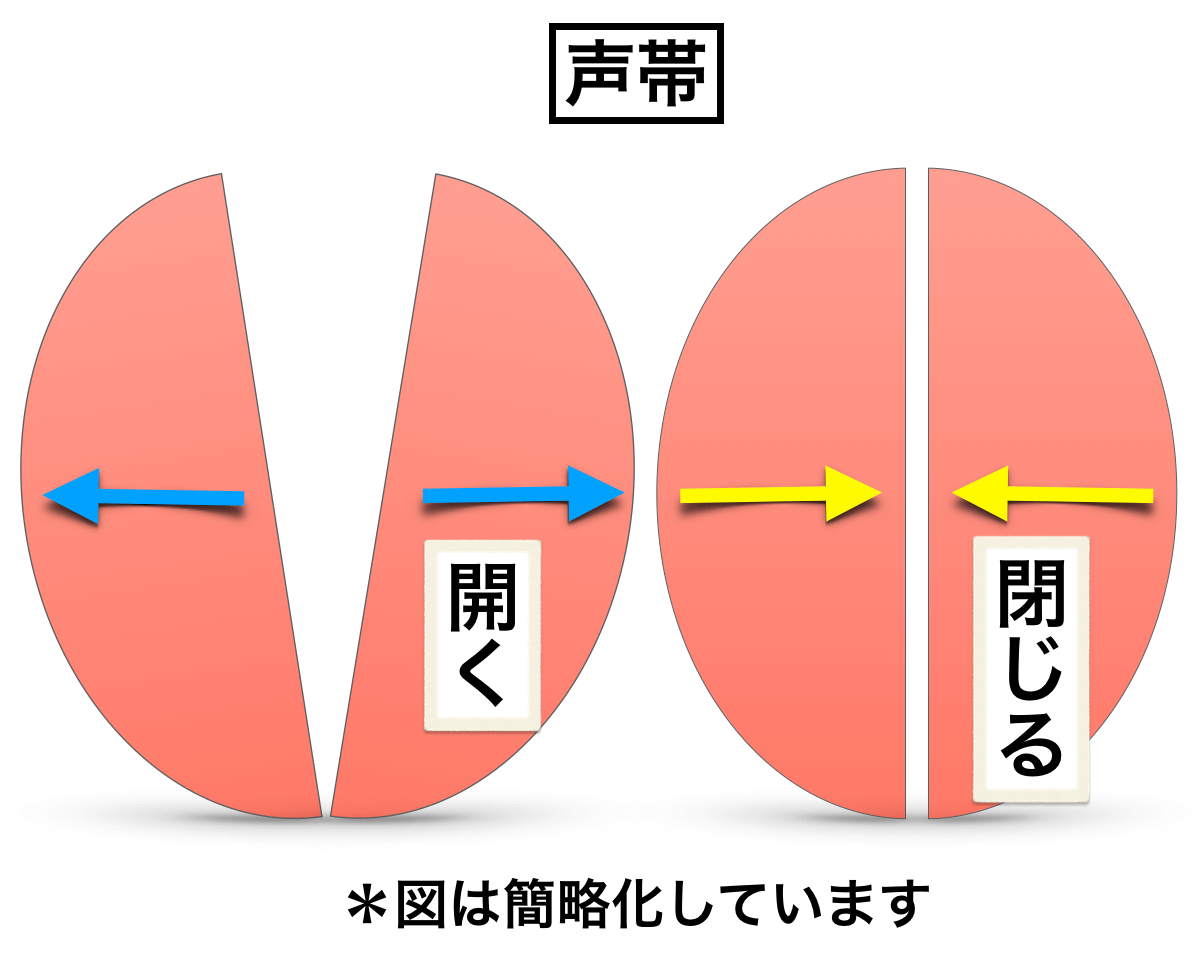
この閉じることによって肺から出てきた空気が声帯にぶつかって、声帯が振動します。
断面から見るとこういうイメージです↓
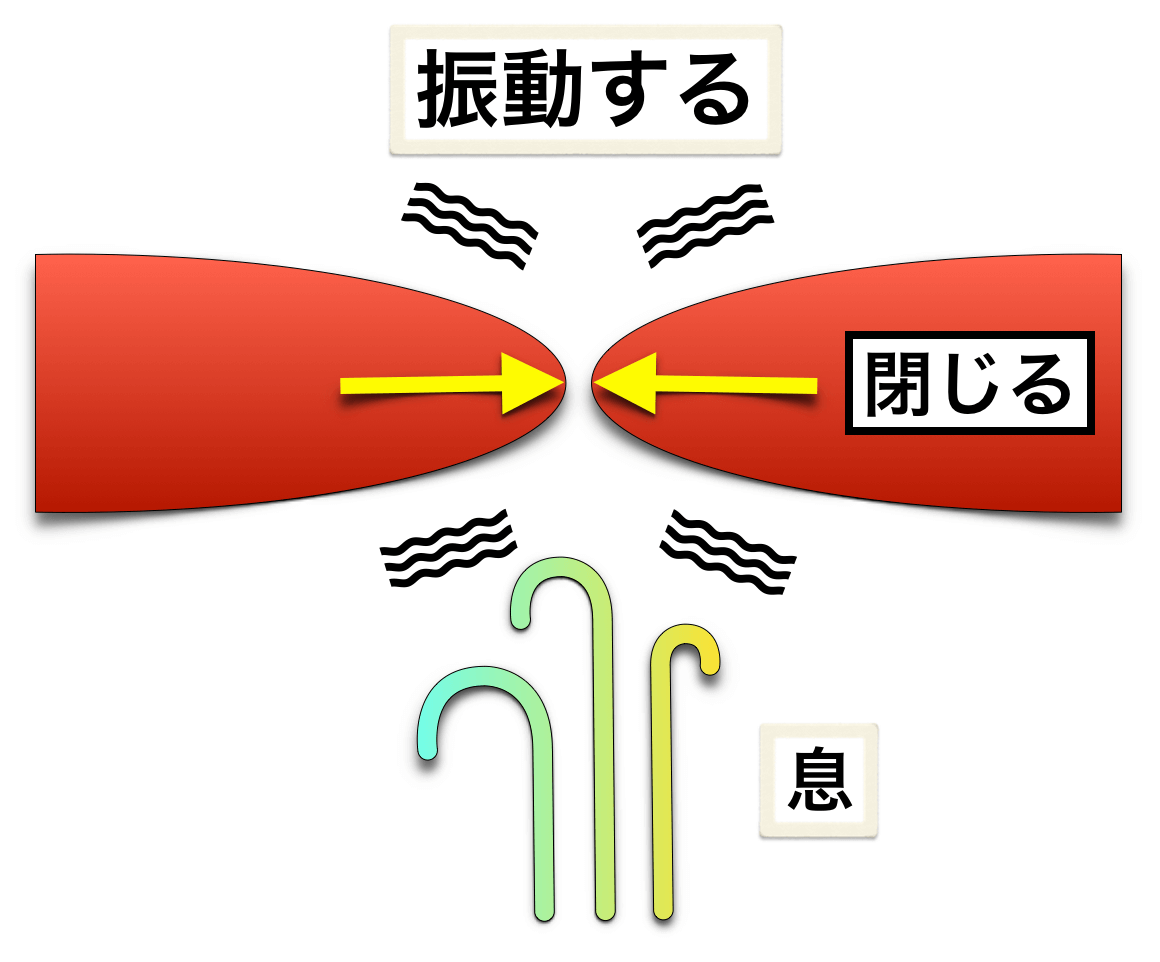
この振動は厳密には「ベルヌーイ」と呼ばれる流体力学によって振動しています。
簡単に言えば「息の流れに吸い付くように振動している」という感じです(*再生位置3:32〜)↓
このような振動によって音(声)が生まれているのですね。
-

-
『声帯コントロール』の鍛え方について
続きを見る
③生まれた音が空間に響く
いわゆる「共鳴」です。
「①息」と「②声帯」によって生まれた音は、主に
- 咽頭腔
- 鼻腔
- 口腔
という3つの空間に響きます。
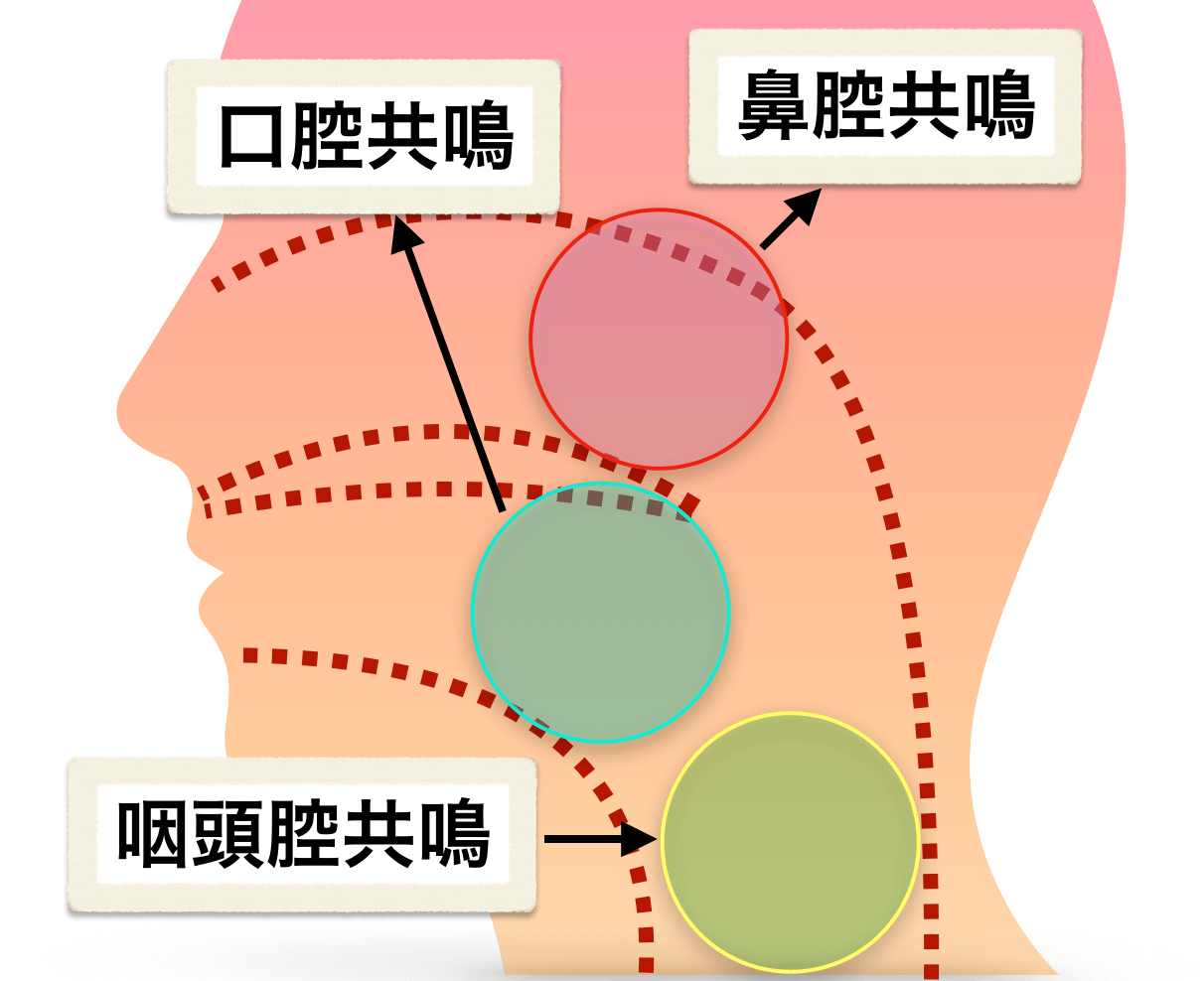
こちらを見ると、より鮮明にイメージできるかと↓
簡単に言えば、声が頭蓋骨の空間の響いているということですね。
-

-
発声における3種類の共鳴について
続きを見る
④発音によって音の種類が決まる
最後は発音の部分です。
- 顎や口の開き具合
- 歯と舌の使い方
などによって発音が決まり、それによって『声』というものが完成すると言えます。
発音に関しては、
- 「声帯の鳴り」+「共鳴の形・顎の開き具合」=『母音』
- 「息」+「歯や舌の使い方」=『子音』
という見方をすることもできます。
これらが声の4要素になる
以上の流れを踏まえると、「①息」と「②声帯」によって生まれた音が「③共鳴」によって増幅して、そこに「④発音」が加わることで声の完成です。
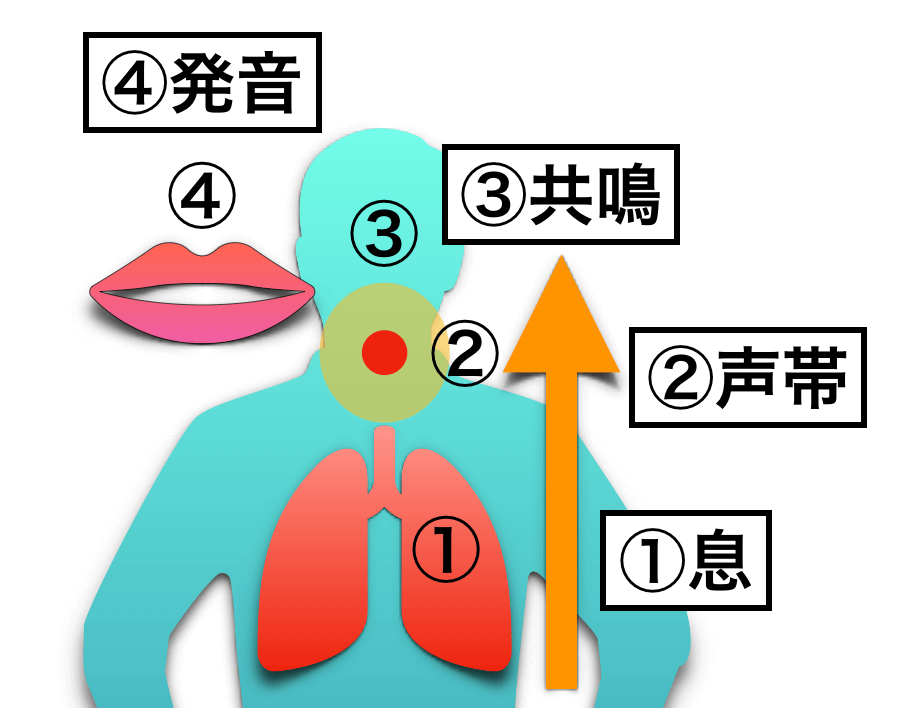
つまり、声は
- 息
- 声帯
- 共鳴
- 発音
という4つの要素になると言えるでしょう。
『歌声に関する何かの問題はこの4つの中に答えがある』とも言えますし、何かを解決したいときなどは「息を〜」「声帯を〜」「共鳴を〜」「発音を〜」のように、この4つから改善すればいいと言えます。
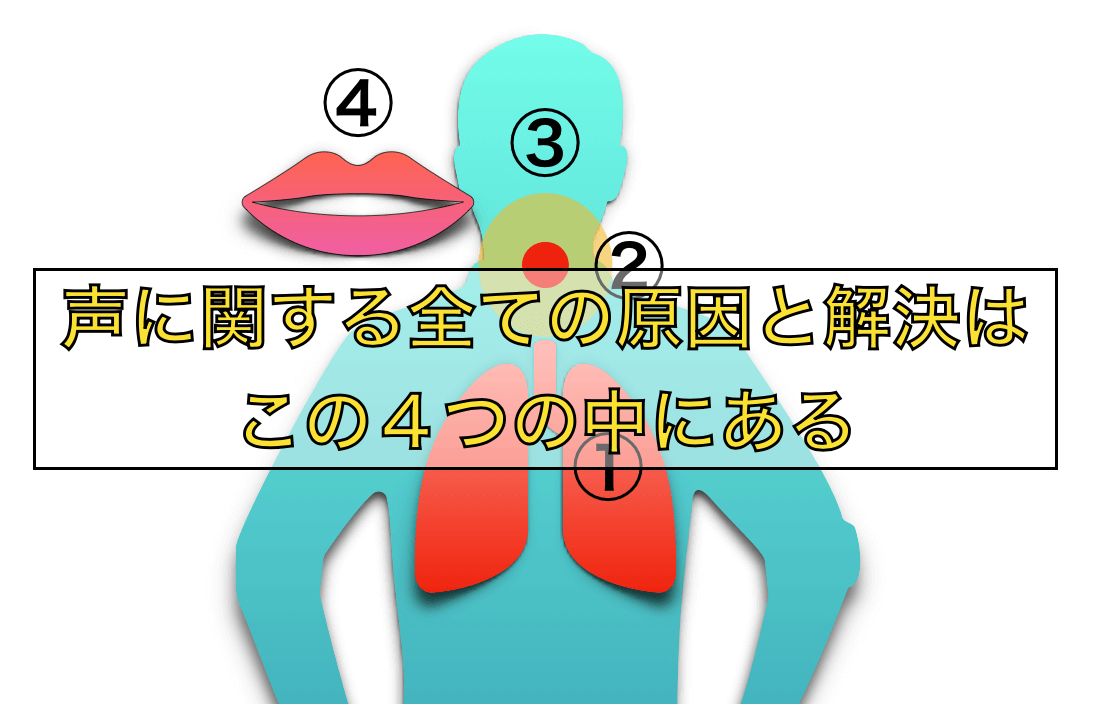
それぞれ4つの要素は繋がっている
ここで一つ重要なのが、4つは密接に繋がっているということ。
例えば、
- 【息と声帯の繋がり】:息を強く吐いても声帯がそれに適応してなければ、それに見合った発声はできない。
- 【声帯と共鳴の繋がり】:声帯の能力不足により、発声時に喉が締まり、共鳴腔が小さくなることで良い発声にならない(=喉絞め発声)。
- 【共鳴と発音の繋がり】:口を縦に開けると太く暗い音色の傾向になり、口を横に開くと細く明るい音色の傾向になる。
などのように、それぞれの繋がりを無視できない問題があります。
つまり、隣り合う能力はお互いに干渉し合っているので、4つは完全に分断して考えてはダメなのですね。
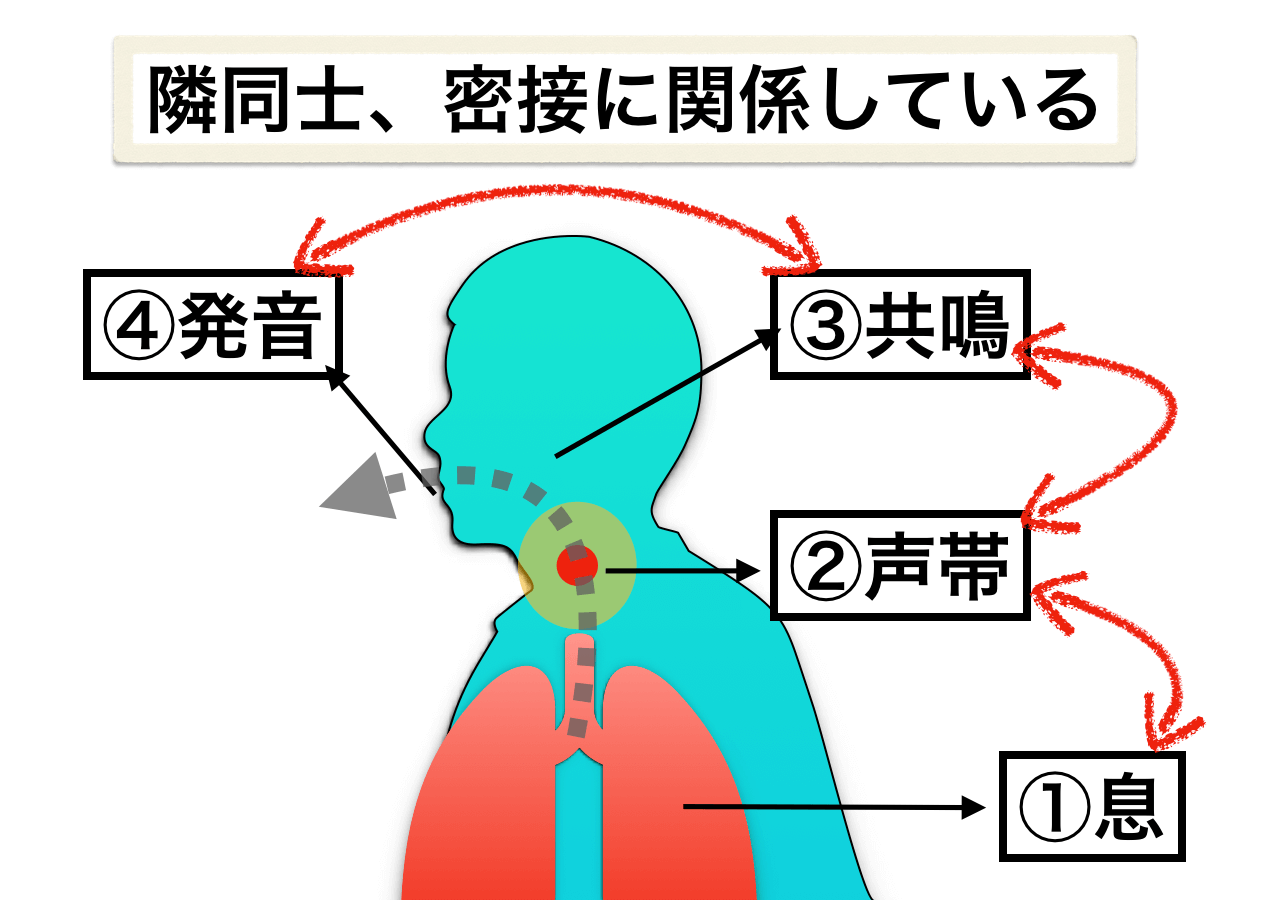
基本的には、声の問題は4つに分解して考えていいのですが、繋がりの部分を忘れないように。
特に『息と声帯の繋がり』に関しては、重要性が高いので意識しておきましょう。
続きを見る

息に声を乗せる【”息の重要性”と声帯との連動性について】
![]()




